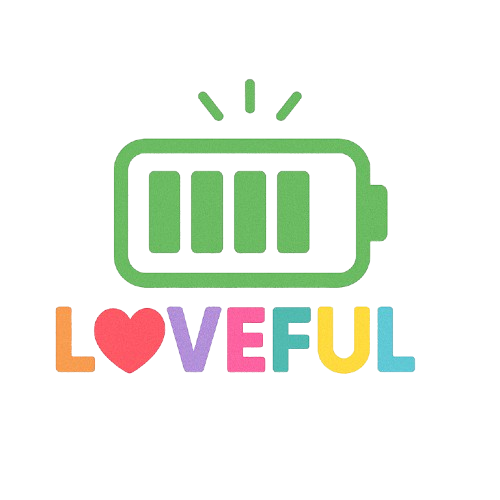結婚のスタイルも多様化している時代ですよね。
そんな中で最近大きな話題になったのが、YouTuberのヒカルさんが発言した「オープンマリッジ」です。
「浮気OK」「ノアもハーレムにいてほしい」――。
こうした言葉は強烈で、多くの人に衝撃を与えました。
SNSでは「自由でいい」という声もあれば、「結婚を軽く見ている」と批判する声もあり、まさに賛否両論。
そもそもオープンマリッジとはどういうものなのでしょうか。
そして、なぜここまで炎上したのか。
今回はその意味やメリット・デメリット、SNSや有名人の声、最後に筆者自身の考えも交えてお伝えしていきます!
オープンマリッジとは何か

「オープンマリッジ」というのは、夫婦が話し合いで合意したうえで、結婚相手以外の人と恋愛や性的な関係を持つことを認め合う結婚スタイルです。
不倫と似ているように感じるかもしれませんが、最大の違いは「合意があるかどうか」。
不倫は隠れて行うものですが、オープンマリッジはルールを作ってお互いに認め合う形です。
- 婚姻関係は続けたまま、関係を開放する
- 透明性や合意が前提
- ルールを守ることが必須
似た言葉に「ポリアモリー(複数人と同時に恋愛する)」や「オープンリレーションシップ(交際関係を開放する)」がありますが、オープンマリッジは「結婚」という制度を前提にしている点で異なります。
ヒカルさんの宣言と炎上した理由

ヒカルさんは交際ゼロ日で進撃のノアさんと結婚した直後に「オープンマリッジ宣言」をしました。
さらに「ノアもハーレムにいてほしい」と発言し、話題は一気に炎上します。
ノアさん自身は「目の前にいるときは私を一番にしてほしい」「好きと思わせてくれないなら離婚」と条件を提示しましたが、多くの人は「ハーレムの一員」という表現そのものに強い違和感を覚えたようです。
- 一夫一婦制が前提の日本の結婚観とのズレ
- 「ハーレム」という言葉が妻への敬意を欠いていると受け取られたこと
- 結婚直後というタイミングでの宣言
- インフルエンサーとしての影響力の大きさ
オープンマリッジに関するみんなの声
もちろん反対派
ヒカル、オープンマリッジとか男都合過ぎ。結婚後に言うのも結婚詐欺。元々浮気OKの価値観なら第三者交えて7時間話し合いにはならず二つ返事なんじゃないの?結婚して安心しつつ独身のように遊ぶなんていいとこ取り。奥さんに一途か独身貫くぜ!の方がかっこいいよ。ほんとにカッコ悪いおじさんですね pic.twitter.com/ddFPceR73w
— 나 (@0meow_8) September 14, 2025
ヒカルさんのオープンマリッジの件でめちゃくちゃ納得したコメントがこれ、
— 🧊 (@__bananauyu__) September 16, 2025
過去に元彼から酷い扱い受けたとかって話をすると、同じように雑に扱ってくる人が寄ってくるのって本当なのかもしれない pic.twitter.com/UTFhVhU7QB
ヒカルとノアのこれ。"オープンマリッジ"がどうこうよりも、もっとやばいのは「自分の苦しみを解放する為なら例え大事な女を苦しめる事になってもいい」と思ってる事。自由とわがままは違うし、わがままに生きたいなら最初から結婚しなきゃいいのに。 pic.twitter.com/Yj6oHBwubD
— ルージュ💄 (@_rouge_1) September 15, 2025
正直少数派な肯定・中立派
そもそもノアの方も浮気OKのオープンマリッジ前提で結婚に同意してるのにヒカルだけ叩かれるの意味わからんよな。批判してる奴らは人気キャバ嬢経て社長やってるような女にすら意志も責任もないと考えてるのか?さすがに女性をばかにしすぎじゃないか? pic.twitter.com/w89EKAknaH
— 恋愛のドグマ🦁マッチングアプリ恋活婚活で幸福を掴ませる (@dogmapua666) September 16, 2025
でもこれ、ノアちゃんも浮気したいからOK出したんだよね🥹
— それいけ❗️あかねちゃん (@mora_nige) September 15, 2025
ヒカルだけ叩かれてるけどノアちゃんも同類、この二人だから結婚したんだろうな🥹
有名なYouTuberがオープンマリッジ公表してたら、数年後にはそれが一つの結婚の形として普及してそう🥹 https://t.co/V9sa3LUskN pic.twitter.com/QlkpzjuP4E
オープンマリッジのメリット

オープンマリッジのあえて言うメリットとしては以下が挙げられます……
- 自由度が高く、息が詰まらない
- 欲求の違いを正直に扱えるのは、救いになる
- 対話が増え、関係の「見取り図」が描ける
- 従来の型にとらわれない家族像を選びやすい
自由度が高く、息が詰まらない
結婚しても「個としての時間」や「自分らしさ」を保ちたい――そんな願いに応えやすいのがオープンマリッジの発想です。
相手に“100点満点”を求めないので、趣味・仕事・交友関係の優先度を柔軟に調整しやすくなります。
「今日は自分の予定を優先していい」「週末はそれぞれの時間を過ごそう」といった線引きができると、息苦しさは和らぎますよ。
ただし、この自由は“合意の上に成り立つ自由”。境界線が曖昧だと、すぐに不安へと変わります。
- 自分時間の確保でストレスが分散
- 期待値の調整で“小さな不満”が溜まりにくい
- 境界線の文書化で自由と安心を両立
欲求の違いを正直に扱えるのは、救いになる
性欲やスキンシップの頻度、恋愛の温度感。夫婦で差があると、どちらかが我慢しがちですよね。
オープンマリッジは、その差を「ダメ」ではなく「事実」として扱います。
抑圧が減ることで、嘘や隠しごとによる傷は避けやすくなります。
ただ、正直さは“聞く側の心の準備”があってこそ。受け止める力が揃っていないと、かえって心に刺さることもあります。
- 我慢の連鎖を断ちやすい
- うそ・隠し事リスクを低減
- 受け止める力を育てる前提づくりが鍵
対話が増え、関係の「見取り図」が描ける
開放の範囲・頻度・報告の方法……。話し合わないと決められないことが多いから、自然と会話は増えます。
“合意メンテナンス”の定期便を作ると、感情の変化にも気づきやすくなります。
「月1回の見直し」「××は事前相談」など、運用ルールを可視化すると、安心感が違いますよ。
- “定期点検”で感情の変化を早期発見
- ルールの可視化で解釈違いを回避
- 会話の質そのものが上がる
従来の型にとらわれない家族像を選びやすい
伝統的な「唯一・永遠」という価値観が合わない人にとって、オープンマリッジは救いになります。
“自分たちの納得”を中心に据え直せるからです。
とはいえ、社会の目はまだ厳しめ。外にどう見せるかという広報設計まで必要になりやすい点は、頭に置いておきたいですね。
- 自分たち基準で関係を設計
- 合う人には大きな安心
- 社会との接点は慎重に
オープンマリッジのデメリットおよびリスク

オープンマリッジには、炎上している通りデメリットやリスクが伴います。
- 嫉妬と不公平感は、想像以上に心が揺れる
- 透明性・報告義務は、やがて心の負荷になる
- 社会的理解が乏しく、外部の目が厳しい
- 子どもへの影響は、最も慎重に考えたい
- 合意は“いずれ変わる”。持続が難しいのが現実
嫉妬と不公平感は、想像以上に心が揺れる
理屈では合意しても、感情は別もの。
「相手の外出が増えている」「自分だけ置いていかれている気がする」――そんな小さな違和感が積み重なると、関係は一気に不安定になります。
比較やランキングの発想が入り込むと、心の安全基地が揺れます。
嫉妬が出たらダメではなく、嫉妬が出たら話すへ切り替えられるかが分かれ道です。
- 自分たち基準で関係を設計
- 合う人には大きな安心
- 社会との接点は慎重に
透明性・報告義務は、やがて心の負荷になる
「事前に言う」「終わったら報告する」。一見フェアですが、常時監視のように感じる瞬間も。
位置情報の共有や逐一の報告は、安心と引き換えに疲労を生みます。
情報量を“必要十分”に絞る基準(誰・何・いつ・どこまで)を合意しておかないと、報告が“取り調べ”になりやすいですよ。
- 安心のための透明性が疲労に変わる
- 報告の“粒度”を合意しておく
- 既読・位置情報に過度に依存しない
社会的理解が乏しく、外部の目が厳しい
職場・親族・ご近所。言わない自由もありますが、どこかで漏れることはあります。
噂話の的になったり、偏見にさらされたり。自分たちだけの問題で終わらないリスクが常に伴います。
話す・隠すの線引き、万一広がった時の対応(説明文、広報役の決定)まで、現実的に準備が必要です。
- 外部の目線はコントロール不能
- 情報管理と説明方針の合意が必須
- 子どもの環境への二次波及に注意
子どもへの影響は、最も慎重に考えたい
誰の子か分からない可能性が生まれる――これは感情論ではなく現実的なリスクです。
家族の物語は、子どものアイデンティティ形成に直結します。
さらに、関係性を公開した場合、子どもが学校やSNSでからかわれる・拡散される可能性も高いですよね?
大人の合意が子どもにとっての最善とは限らない。この非対称性は、常に心に留めたい点です。
- 親の選択が子の安全基地を揺らす
- パタニティ・プライバシーの課題
- “子の最善”を軸に再検討を
合意は“いずれ変わる”。持続が難しいのが現実
始めたときの気持ちと、続けるときの気持ちは違います。
「最初は平気だったことが、ある日急に無理になる」――人の心は変わりますよね。
定期見直しと退出プラン(いつ・どうやってやめるか)を決めていないと、関係は容易に破綻します。
- 合意には賞味期限がある前提で
- 見直し会議と退出条件をセットで
- “やめる勇気”も関係の成熟
法的リスクは想像より重い
日本の制度に「オープンマリッジ」はありません。
不貞の解釈や慰謝料、親権争いに波及する可能性は常にあります。
合意書が万能ではない点も現実です(法的有効性は限定的)。
ここは専門家への相談が欠かせません。
(※本セクションは一般的情報であり、法的助言ではありません)
- 制度の傘がない=トラブル時に脆い
- 合意書の限界を理解する
- 早めの法的リスクチェックを
筆者の私見
夫婦で話し合った結果、オープンマリッジに対しては反対意見でした。
二人で愛し合っているからこそ、このオープンマリッジ宣言は衝撃で……
具体的にどういった意見があったのか、お伝えしていきます!
一途な気持ちはやはり強い
結婚は“唯一の相手として選び合う”という約束の物語です。
「ハーレム」「開放」といった言葉が差し込まれた瞬間、その物語は揺れます。
安心の土台が揺らぐと、良い時は楽しくても、悪い時の耐久性が落ちるのです。
危機の時こそ“唯一の絆”が効く。ここを弱める設計には賛同しにくいというのが率直な立場です。
- 唯一性は危機対応の“備え”
- 言葉選び一つで信頼が傷つく
- 物語の一貫性が安心を生む
子ども最優先で考えると反対
結婚関係の不確実性は、家庭の安定に直結します。
また、関係性の公開はデジタルに半永久で残り、子どもが将来それに触れるかもしれませんよね?
からかい、いじめ、SNS拡散。現実には起き得る出来事です。
「大人の自由」と「子の最善」を秤にかけたとき、私は後者を優先すべきだと考えます。
- プライバシーの重大リスク
- デジタルタトゥーは消せない
- “子の最善”の視点でブレーキを
公開宣言は、二次被害の火種に
関係の形を公にすることは、説明責任と炎上リスクを常に背負うことです。
好奇の目は、やがて悪意の矢じりに変わります。
当人だけでなく、親族・職場・子どもまで影響の輪が広がる点を無視できません。
話す自由と同時に、話さない権利も守るべきです。
- 公開=説明責任と炎上の常在化
- 影響は同心円状に広がる
- プライバシーの設計が不可欠
合意に見えても、力関係が歪むと同意ではなくなる
「嫌と言えない空気」があると、合意は合意ではありませんよね。
経済力・知名度・年齢差・依存度――力の偏りは判断を鈍らせます。
“うなずいた”という事実だけでは足りません。安全に断れる環境までセットで、はじめて対等です。
- 合意は“断れる自由”が前提
- パワーバランスの偏りは危険信号
- 外部相談先の確保が抑止力に
実装難易度が高すぎて、現実解とは言いにくい
理屈は美しくても、運用は繊細です。
感情、時間、情報、法、周囲――管理項目が多すぎますよね。
カップル療法や関係教育で対話を鍛えること、まず排他的関係の中で信頼を深める努力を重ねること。
それでも満たされない課題が残った時の“最終手段”として考えるのが、現実的ではないでしょうか。
- 感情と制度の両輪が必要
- まずは排他的関係の質を上げる
- “最終手段化”で被害最小化
オープンマリッジに関するQA
ここからは、オープンマリッジについてよく聞かれる疑問を、分かりやすくまとめてみました。
Q1. オープンマリッジって、不倫とどう違うんですか?
不倫は片方が隠れて関係を持つことですが、オープンマリッジは「合意の上でルールを作る」という点が大きな違いです。
ただし、合意していても心の負担がゼロになるわけではなく、実際には難しいことが多いですよね。
Q2. 日本の法律で認められているんでしょうか?
法律上は一夫一婦制が前提なので、オープンマリッジという制度は存在しません。
夫婦の合意にとどまるため、もし離婚や慰謝料の問題が起きれば「合意していた」としてもトラブルになりやすいのです。
Q3. 海外では当たり前なんですか?
海外でも「当たり前」といえるほど普及しているわけではありません。
欧米では一定の理解はありますが、賛否は大きく分かれており、文化や宗教観によって受け止め方は大きく異なります。
Q4. 子どもができたらどうなるんでしょう?
これは非常に大きな問題です。
父親が誰か分からなくなるリスクがあり、さらに「親がオープンマリッジをしている」と知られれば、子どもの立場が悪くなることも考えられます。
大人同士の関係だけでは済まない点が、深刻ですよね。
Q5. もしやってみたいと思ったら?
どうしても選びたいなら、徹底した話し合いが必要です。
- ルールを具体的に決める
- 隠しごとはしない
- 「気持ちが変わるかもしれない」という前提を持つ
オープンマリッジをするかどうかは個人の自由!ただ周りの目は厳しいかも
オープンマリッジとは、夫婦が合意して結婚関係を開放するスタイルです。
自由や対話を増やす可能性がある一方で、嫉妬・不信・子どもへの影響といった大きなリスクを抱えています。
ヒカルさんの「ハーレム発言」は、そのリスクを象徴するようなものでした。
松浦会長など有名人からの批判もあり、炎上はさらに広がりましたよね。
最終的に大事なのは「夫婦にとって何を一番に守りたいか」です。
自由を選ぶのか、唯一性を守るのか。
その問いを考えることこそ、結婚生活を続けるうえで欠かせないことなのだと思います。